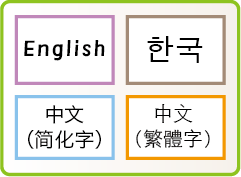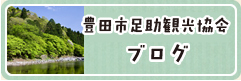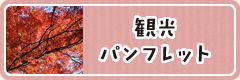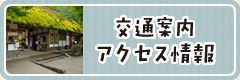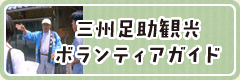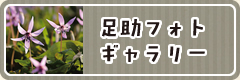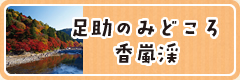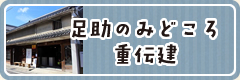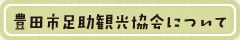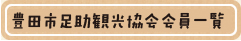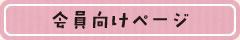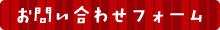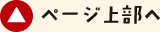令和7年4月12(土)13日(日)足助春まつり(足助神社例祭・重範祭)※雨天決行

足助神社は、足助八幡宮の東となりにあり、元弘の乱(1331)に、南朝・後醍醐天皇を守り、笠置山(京都府)で奮戦した足助次郎重範公(あすけじろうしげのり)を称える祭りです。かつては重範公の命日にちなんで5月3日に行われていましたが、最近は桜の咲く季節の4月の第2日曜日とその前日に執り行われています。おまつりは、足助地区中心部にある7つの町(親王町、田町、本町、新町、西町、宮町、 松栄町)が花車を出し、町内を曳き回します。
この花車は、桜、藤などで美しく飾られており、10代までの女の子が囃子方の笛に合わせて太鼓をたたき、歌を歌います。
そして、若連と呼ばれる20代が中心の男衆が花車の梶をとり、足助の町並みを練り歩きます。
男性的で勇壮な秋祭りに対し、春まつりは、華やかな女の子の祭りといわれています。
| 住所 | 足助神社 |
|---|---|
| TEL | 0565-62-0516 |
| 開催場所 | 足助神社 |
| 日にち | 試楽祭(町内引き廻し) 令和7年4月12日(土) 13時30分~18時 本楽祭 令和7年4月13日(日) 6時30分頃~19時 |
今年のポスターは、本楽13日(日)に行われる宗家柳生耕一氏による柳生新陰流剣術奉納と、それを頼もしく見守っている足助次郎重範さん(イメージ)
その前には、松栄町・宮町・西町・新町・本町・田町・親王町の7台の華やかな花車と若衆さん、そして親王町の子ども花車が並んでいる様子が描かれています。絵:柄澤照文氏
【4月12日(土)】
13時30分~:各町内を花車運行
【4月13日(日)】
6時30分~ :宮入に向け、各町内を花車順次出発
10時30分~:例祭・追善法要・・・京都 笠置寺(かさぎでら)住職による
11時50分~:神前に花車集まり、お囃子を奉納
12時30分~:宗家柳生耕一氏による柳生新陰流剣術奉納
16時~ :各町内に花車が引き返す
春まつり内容・経路図
※雨天決行。ただし、一部変更がある場合があります。
土曜日<試楽>
この日は、午前中に花車を組み、14時から各町の範囲内で引き廻します(花車が集まっての運行ではありません)。
夕方17時くらいに終わります(町によって終了時間が違います)。
日曜日<本楽>
朝、6時30分に松栄町からスタート。
順に宮町・西町、新町、本町、田町、親王町が動き出し豊田森林組合まで進行。
午前8時40分、森林組合を出発した7台の花車は香嵐渓前・西町入り口付近に一時集結します。
午前11時、7台の花車が列をなして国道を通行し、足助神社へと向かいます。
足助八幡宮の信号を左折して宮町駐車場内を通り、巴川沿いの裏道に出て右折し、足助神社へ向かいます。
午前11時50分より、神社前に花車を進め町内ごとにお囃子を奉納します。
お囃子奉納を終えた花車は足助支所前に並びます。
その後、休憩を取り、16時ごろ花車が停車している足助支所前から出発し、各町へと帰っていきます。
夕方18時~一番遠くの田町へは19時ごろに到着します。
4月13日(日)の午前11時からと、午後4時からの少しの間、山車の運行のため一部交通規制が行われます。
道路が混み合う場合がございますが、ご理解ご協力をお願いします。
【足助神社】例祭限定御朱印について
<授与期間>
令和7年4月1日~20日
初穂料 500円
※紙の授与のみとなります。
春まつり(足助重範祭)限定の御朱印です。
こちらは足助八幡宮の4月限定御朱印です。
あわせてどうぞ。
足助重範と柳生家の関係
鎌倉時代1331年、9月 鎌倉幕府打倒を企てる後醍醐天皇と共に京都笠置山に立てこもり幕府との戦い(元弘の乱)で総大将として大手門を守備したのが足助重範、搦手(からめて)(裏門)を守備したのが柳生一族の始祖といわれる柳生永珍(ながよし)。戦友であります。