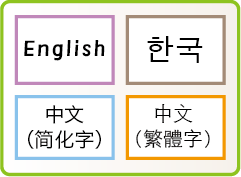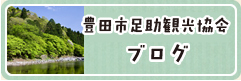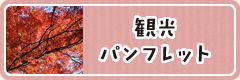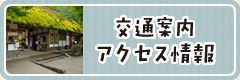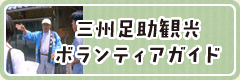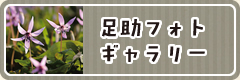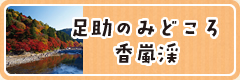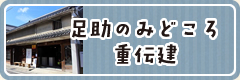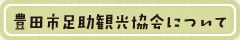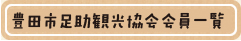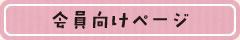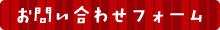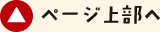毎年1月7日『足助八幡宮七草粥』※無料 (屋外またはテイクアウト)

1年間の無病息災を願い、七草粥の炊き出しが行われます。
どうぞお参りください。
| 住所 | 足助八幡宮境内 |
|---|---|
| 日にち | 令和8年1月7日(水) |
| 時間 | 午前11時より、なくなり次第終了 |
| 料金 | 無料※駐車場有料500円 |
初詣にはお出掛けされましたか?
1月7日(水)午前11時より毎年恒例の「足助八幡宮 七草がゆ」が行われます。
たくさん用意しておりますが、数に限りがございますのでお早めにお越しください。
温かい炊き出しを行うのは、足助のAT21倶楽部の皆さんです。
お手伝いは足助の観光ボランティアガイドさん達。
八幡宮には足腰のお守りや足形の絵馬、ご朱印もあります(^^♪
神社の駐車場はございませんので、香嵐渓駐車場(有料)P1宮町駐車場をご利用ください。
お粥を食べた後は是非、足助の古い町並みや香嵐渓の散策をお楽しみください。
毎年恒例の“七草粥”を行います(^_-)-☆
屋外(境内に小さなイスが並べてあります)で、暖かいお粥をお召し上がりください。
テイクアウトも出来ます
(蓋つきの容器をビニール袋に入れてお渡しします)
体調のすぐれない方はご来場をお控えください。
揚げもちは行いませんのでご了承ください。
“七草粥”は無病息災を願う日本の伝統文化です。
たくさん用意しておりますので、どうぞお越しください。
※駐車場は別途有料となります。
平日は、足助支所駐車場は支所利用者しかご利用できません。
足助八幡宮向かい側のP1宮町駐車場をご利用ください。
七草がゆとは
七草粥の風習は中国より伝わり、室町時代にお粥に代わっていきました。現在ではお正月の行事として定着していますが、本来1月7日の「人日(じんじつ)」の日に行われる五節句の中の1つの行事です。
なぜ「人日」と言うのでしょう?
古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狛(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていました。そして、7日目を人の日(人日)とし、犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていたそうです。そして、この日には7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの)を食べる習慣があり、これが日本に伝わって“七草がゆ”となりました。
使われている春の七草は早春の頃一番に芽吹くもので、邪気を払い無病息災を願って食されています。正月に飲み食いして疲れた胃を休め、日常の食生活に戻る1つの区切りとなっています。
[春の七草の効能]
セリ・・・ ビタミンCが豊富で、鉄分・食物繊維を多く含み貧血や便秘に効果あり
ナズナ ・・・ 高血圧を予防します
ゴギョウ・・・ 胃炎をしずめ、咳・たん・熱を取り風邪の予防に効果あり
ハコベラ・・・ 整腸効果、利尿作用、口臭予防
ホトケノザ・・・健胃効果、解熱作用あり
スズナ ・・・ 整腸効果あり
スズシロ・・・ 整腸効果あり