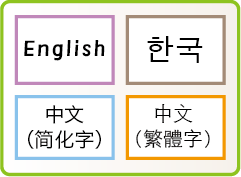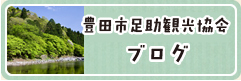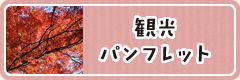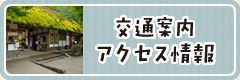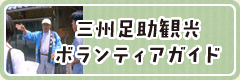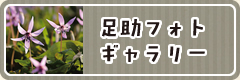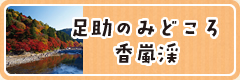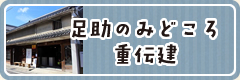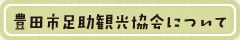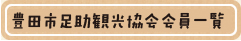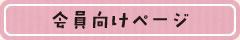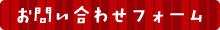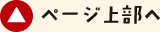★6月2日より募集開始★令和7年6月22日(日)第9弾!『御朱印10か所+2(紙屋鈴木家印と足助宿印)中馬街道足助宿~ご朱印めぐり~』

足助は江戸時代後期から明治にかけ飯田街道(通称:中馬街道=塩の道)の宿場町、物資の中継地として栄えた町。そのため、街道沿いにはパワースポットのお寺やお堂が多くあります。毎月22日に公開の香嵐渓太子堂もコースに加わり、旧鈴木家の御家印や足助宿印も集めて回ります。元祖中馬街道を行く往復6.5キロのコースで、御朱印を集めながら足助の歴史と文化、ご当地スイーツを味わってください。


【申込み】令和7年6月2日(月) 午前9時より
電話またはFAXで豊田市足助観光協会まで
電話:0565-62-1272
FAX:0565-62-0424
※定員(先着100人)になり次第受付終了
日 時
令和7年6月22日(日) 午前9時30分~午後2時
※受付は足助八幡宮にて午前9時30分~10時までにお済ませください。
※午後2時までに終点でお土産と引き換えてください。
※雨天決行
※約6.5キロを歩きます。
寺院・お堂
足助八幡宮、足助神社、太子堂、香積寺、馬頭観音、旧鈴木家住宅(紙屋)、本町地蔵堂、旧田口家住宅、本町庚申堂、慶安寺、お釜稲荷社、宝珠院
内 容
足助八幡宮にある受付で名札と地図を受け取り、御朱印10枚と御家印1枚、御宿印1枚を歩いて集め、曲げわっぱのKIKIで参加記念のお箸をもらいます。休憩所では、足助の菓子屋3店舗のスイーツの中から2個を選んでお召し上がりください。
参加費
3,000円/人 ※当日に現金のみ
(御朱印10枚、その他2枚、お菓子2つ、記念のお箸、御朱印めぐりオリジナルてぬぐい)
※市営駐車場は別途、有料500円が必要です。
※もらえる御朱印は書置きした別紙です。ご朱印帳への記帳は別途料金が必要です。 (記帳が出来ない場所もあります)
対 象
子どもから大人まで
※お付き添いは無料です
※ペット同伴は不可
ご確認事項
・あらかじめ用意された別紙のご朱印です。
一部の社寺では、お持ちのご朱印帳に書くことも出来ますが、別途料金がかかります。
当日に各社寺にお伺いください。
・参加するには事前の予約が必要です。
・申込者のお連れ様やお子さんが一緒に歩かれることは自由です。
・性別や年齢制限はございません。
・寺社仏閣が含まれますので、ペット同伴は不可です。
・駐車場は宮町駐車場または足助支所駐車場が近くて便利です。(別途料金500円)
全12か所の御朱印めぐりスポット
①足助八幡宮(受付)
673年の創建と伝えられ、本殿は国の重要文化財にも指定されています。
古くから足、旅、交通の守護神として信仰されてきました。
②足助神社
弓の名手であった鎌倉時代の武将、足助次郎重範を祀る神社です。
重範は後醍醐天皇が笠置山で挙兵した際、籠城軍総大将として活躍しました。
③香嵐渓太子堂
聖徳太子の恩徳をたたえて、昭和6年に建立されたお堂です。
法隆寺の夢殿を模しており、中には聖徳太子の像が祀られています。
④香積寺
1427年、足助氏の居館跡に創建された曹洞宗の禅寺です。
香嵐渓のもみじは、香積寺十一世の三栄和尚が植えたことからはじまりました。
⑤馬頭観音
足助の町の入り口に位置し、伊那街道を行き交う旅人や馬を見守る観音様です。
松尾芭蕉の句碑も建立されています。
⑥旧鈴木家住宅(紙屋)
かつて足助の豪商であった鈴木家が、ここで長い年月を過ごしてきました。
国の重要文化財として保存修理工事を進めています。
※ここでは「紙屋鈴木家印」をお渡しします。
⑦本町地蔵堂
願いを叶えてくれる「抱き地蔵」と、痛いところと同じ部分をさすると治るとされる「おびんずるさん」がいらっしゃるお堂です。
⑧旧田口家住宅(御宿印)
江戸時代末期の建物で、平入の屋根が特徴的なかつての商家です。
館内にはガソリンタンクのマンホールが残されています。
※ここでは「足助宿御宿印」をお渡しします。
⑨本町庚申堂
小さな境内には「八万の陽石」と呼ばれる男根形の石造物があります。
県内屈指の大きさを誇り、子宝や難病の快癒にご利益があるとされます。
⑩慶安寺
境内にはこの地方では珍しい立派な弥勒菩薩の石像があります。
また門前付近からは奈良時代の須恵器が出土し、田町遺跡としても知られています。

⑪お釜稲荷
どれだけ食べてもなくならないという伝説が残る大きな一升釜と、そのご飯をふるまった平八稲荷を祀る神社です。

⑫宝珠院
鎌倉時代の創建といわれる浄土真宗の寺院です。
境内には江戸時代随一の念仏行者といわれる徳本上人の名号石があり、
お寺から少し行くと、大給松平家先祖の墓もあります。
お土産渡し処 曲げわっぱのKIKI
日本の伝統工芸品である「曲げわっぱ」などを扱うお店です。
こちらで記念ロゴ入りの箸を受け取ってゴールです!お疲れ様でした。